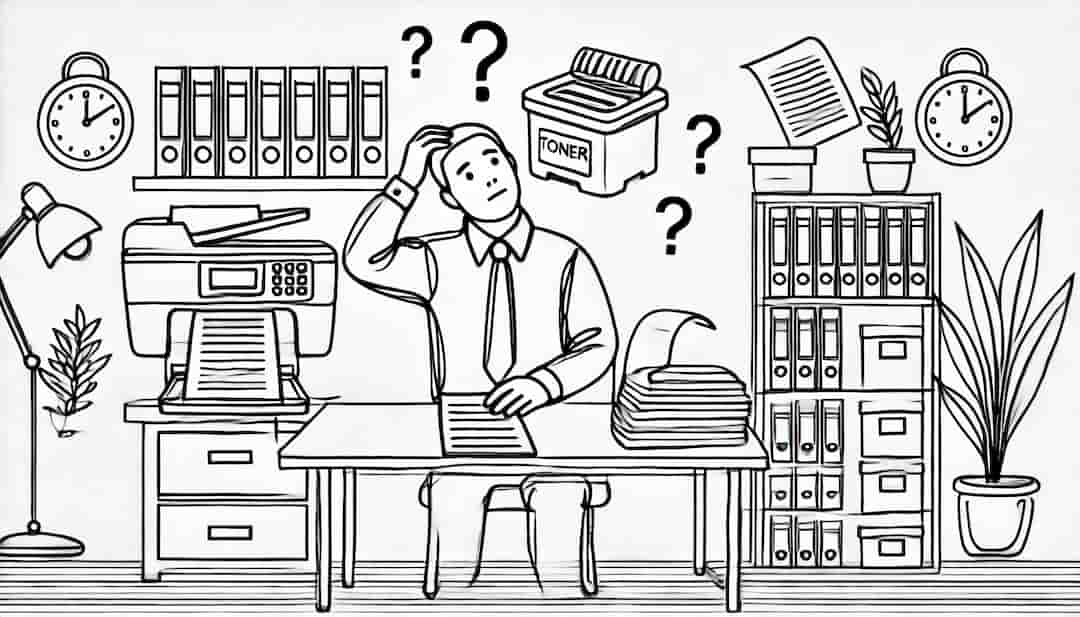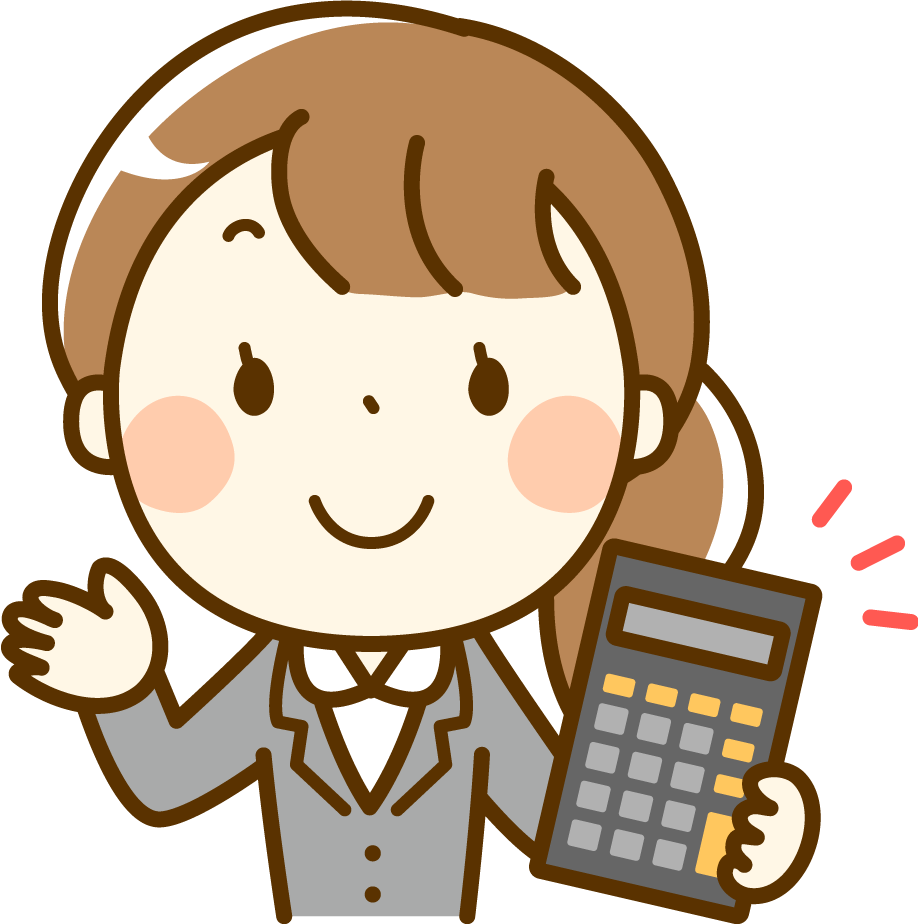「トナーの勘定科目って、消耗品費でいいの?」
経理・総務担当者なら、一度はこんな疑問を感じたことがあるかもしれません。実はトナーカートリッジの会計処理には、明確な「正解」がないことも多く、会社の規模や運用ルールによって勘定科目が分かれるのが実情です。
本記事では、トナーの仕訳でよく使われる勘定科目の選び方や、処理方法に迷ったときの考え方を具体的なケースに分けて解説します。仕訳入力や経費精算でモヤモヤしがちな方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- トナーは何費?まずは勘定科目の基本を押さえよう
- トナーの用途・購入単位で勘定科目が変わるケース
- 仕訳登録時に迷わないためのチェックリスト
- トナーの処分や買取時の会計処理についても知っておこう
- まとめ|トナーの勘定科目は「使い方」と「社内ルール」で決まる
トナーは何費?まずは勘定科目の基本を押さえよう
「トナーって、結局どの勘定科目に分類すればいいの?」
会計処理や経費精算の場面で迷いやすいポイントのひとつです。トナーカートリッジは事務所で日常的に使われる備品である一方、消耗の早さや単価の違いにより、勘定科目の判断基準が分かれがちです。
まずは、トナーに関連する代表的な勘定科目とその基本的な考え方を押さえておきましょう。
「消耗品費」とは?
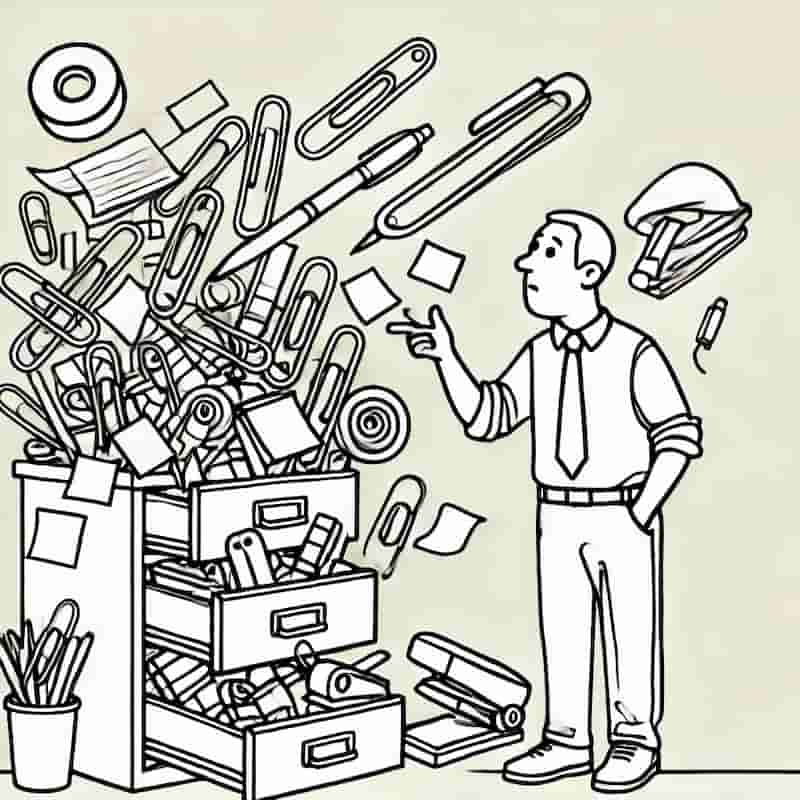
「消耗品費」とは、短期間で使い切る備品や、単価が一定額以下の物品の購入費用に使用される勘定科目です。
文房具・文具類・USBメモリ・クリーナーなどと並び、トナーもこのカテゴリーに分類されることが一般的です。
多くの企業では、購入単価が10万円未満(少額資産扱い)で、使用期間が1年未満のものを消耗品費に含めて処理しています。
トナーは基本的に印刷機器の消耗品であり、使えばなくなる性質のものなので、日常的な補充や単品購入であれば「消耗品費」で問題ないケースが多いです。
「事務用品費」との違い

「事務用品費」も同様にトナーの仕訳で見かけることがある科目ですが、こちらは文房具やペン、用紙などの“事務作業用の消耗品”をまとめて処理する際に使われることが多い科目です。
「消耗品費」よりも用途が狭く、帳簿管理の観点で「事務用品だけ分けておきたい」というポリシーがある場合に選ばれる傾向にあります。
どちらの科目でも処理自体が大きく変わるわけではありませんが、社内ルールに従い、どちらかに統一しておくことが重要です。
同じトナーでも、月によって科目が変わってしまうと、経理上の整合性に影響します。
勘定科目は会社によって変わるの?
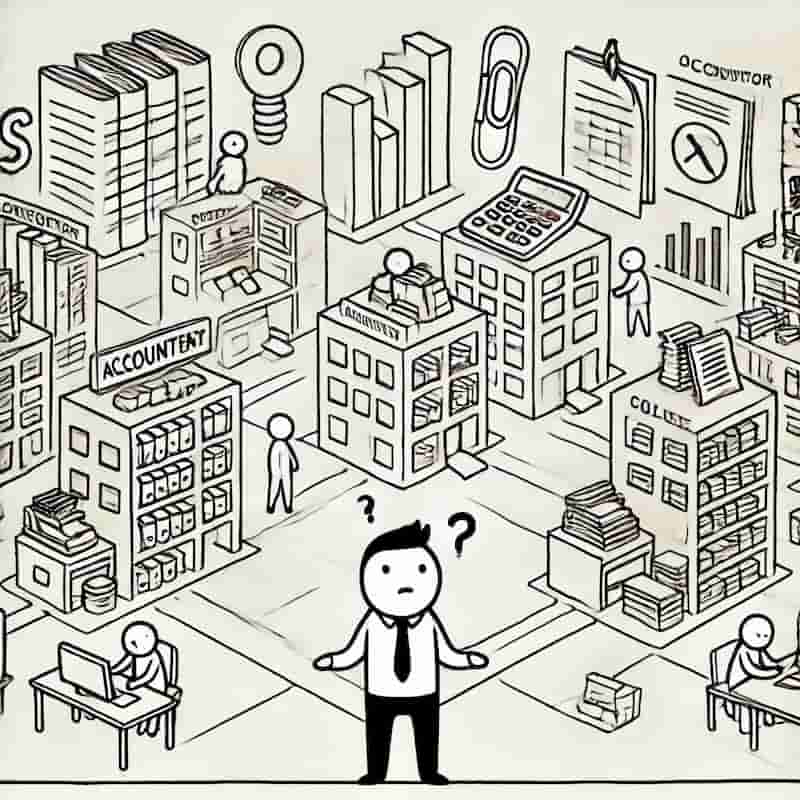
はい、トナーの勘定科目は「正解がひとつ」ではなく、企業ごとの運用方針に左右されます。
たとえば以下のように分かれるケースがあります:
- A社:すべて「消耗品費」で統一
- B社:トナーは「事務用品費」、それ以外の備品は「消耗品費」
- C社:部署ごとに会計処理が異なり、精算システム上で科目が分かれている
このため、他社の仕訳をそのまま参考にするのではなく、自社の経理ルールや過去の仕訳履歴を確認することが大切です。
社内での運用が曖昧な場合は、会計士や税理士に相談したうえで、明確に決めておくことをおすすめします。
トナーの用途・購入単位で勘定科目が変わるケース
トナーは基本的に「消耗品費」で処理されることが多いですが、購入形態や使用目的によっては、別の勘定科目が適している場合もあります。
ここでは、具体的な購入パターンごとに、勘定科目がどう変わる可能性があるかを整理します。
少量購入 → 消耗品費

1本単位や少量で購入し、購入した月のうちに使い切る・使用開始する予定がある場合は、「消耗品費」で問題ないケースがほとんどです。
これは、トナーが使い切りの備品であり、資産として計上する必要がないためです。
例えば:
- トナー1本(8,000円)を月末に購入し、当月中に使用
- 補充目的で必要数だけ発注した場合
このような日常的な購入パターンは、消耗品費としてシンプルに処理できます。
まとめ買い・在庫化 → 貯蔵品や資産管理の対象に?
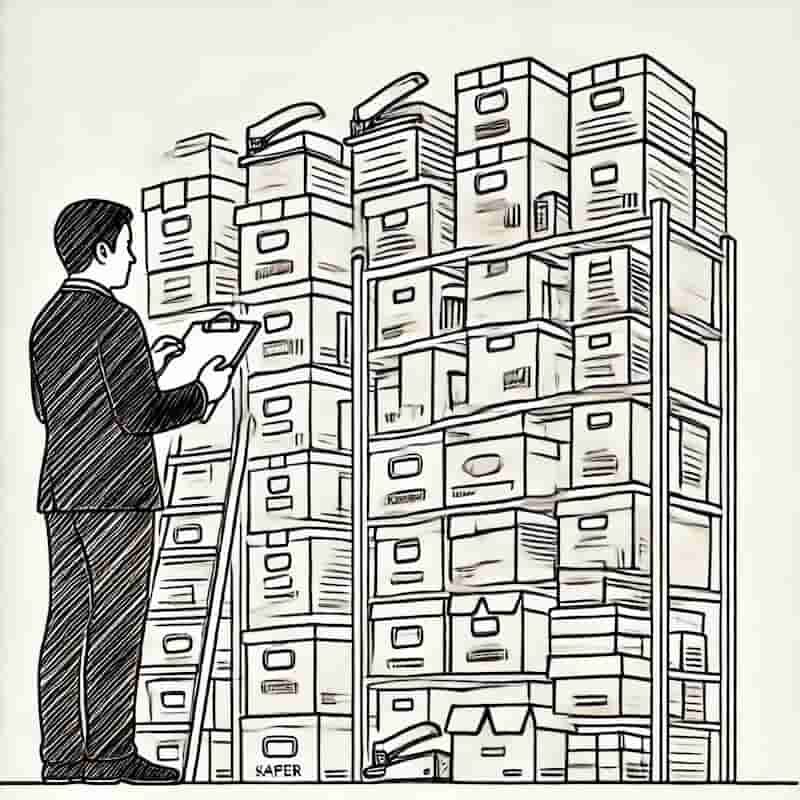
トナーを数十本単位などでまとめて購入し、倉庫や備品棚に長期保管するような場合は、「貯蔵品」として資産管理対象になることがあります。
特に決算月をまたぐ在庫の場合は、以下のような対応が求められることもあります:
- 会計処理上、購入時点では「貯蔵品」扱いにし、使用時に「消耗品費」へ振替える
- 期末棚卸しにより「未使用在庫」を資産計上(間接的に費用化を抑制)
ただし、中小企業や簡易会計を採用している会社では、原則として一括で「消耗品費」に含める処理が多く見られます。
仕訳ルールの適用は、会社の方針や会計事務所の指導方針によって異なります。
コピー機・リース費と一緒に処理するケース
一部の企業では、コピー機やプリンターの使用に伴って定期的にトナーが納品される契約(=保守契約、リース契約)を結んでいる場合があります。
この場合、トナー代が「カウンター料金」や「保守費用」に含まれており、トナー単体の勘定科目が発生しないことがあります。
このようなケースでは:
- 契約上の費用は「リース料」「保守費」「機械使用料」などで処理
- トナーは消耗品費には含めず、包括費用として管理される
会計的には合理的な処理ですが、実務でトナーの残量管理や再発注が必要になる場合は、備品台帳や在庫表での把握が重要になります。
仕訳登録時に迷わないためのチェックリスト
「結局、どう判断すればいいのか?」という方のために、トナーの会計処理で迷ったときの判断フローと入力例をご紹介します。
日々の仕訳登録や経費精算で活用できるよう、実務寄りの視点でまとめました。
✅ 勘定科目の選び方フロー

以下のフローに沿って考えると、科目選択の迷いが軽減されます:
コピー機リース契約に含まれている
→ 「保守費」「リース料」など契約費用で処理
1本〜少量購入 or すぐに使用予定
→ 「消耗品費」で処理(一般的なケース)
文房具や事務用品と一緒に購入した場合
→ 「事務用品費」も選択肢(社内ルールに準拠)
大量購入して倉庫保管・長期未使用
→ 「貯蔵品」処理(棚卸対応が必要な場合)
🧾 会計ソフト・経費精算システムでの入力例
以下は、代表的な仕訳のイメージです。
▶ 消耗品費として処理する場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 8,000円 | 現金 or 普通預金 | 8,000円 | トナー購入(CRG-045) |
▶ 事務用品費として処理する場合(会社ポリシーによる)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 事務用品費 | 8,000円 | クレジット(未払金) | 8,000円 | トナー購入(Canon) |
▶ 貯蔵品で一時処理 → 後日費用化する場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 40,000円 | 普通預金 | 40,000円 | トナーまとめ買い |
※ 決算整理仕訳で「消耗品費/貯蔵品」の振替処理を行う必要あり
⚠ 注意:固定資産ではないが管理が必要なケースも
トナーは一般的に固定資産には該当しません(耐用年数1年未満、少額)。
しかし、以下のような理由で実質的に“備品管理”の対象として扱うべきケースもあります:
- 高価な大容量トナー(数万円〜)をまとめて購入した
- 倉庫に長期保管され、棚卸資産として扱われている
- 部署ごとに在庫管理・使用量管理が必要とされている
このような場合は、会計上は消耗品費で処理しても、台帳やスプレッドシートで管理する社内体制の整備が重要になります。
トナーの処分や買取時の会計処理についても知っておこう
トナーは購入するだけでなく、使われずに余ったり、機種変更や移転で不要になったりすることも多い備品です。
こうしたトナーを「捨てる」のではなく「売る」または「処分する」といった場合、会計処理にも影響することがあります。
ここでは、未使用トナーを手放す際の仕訳や注意点について解説します。
未使用トナーを買取に出したときの仕訳
不要な未使用トナーを専門業者に買い取ってもらった場合、会社としては在庫の現金化(資産の回収)にあたるため、収益計上が必要です。
代表的な仕訳例は以下のとおりです:
▶ 買取価格を「雑収入」として処理するケース
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 現金( or普通預金) | 15,000円 | 雑収入 | 15,000円 | トナー買取代金(CRG-045H) |
※帳簿上「消耗品費」で計上していた場合でも、売却時点では収益化される扱いになります。 なお、減価償却資産ではないため固定資産売却益などでは処理しません。
廃棄したときは「雑損失」?「消耗品費」?

トナーを破損・漏れ・劣化などで使用不能となり、廃棄した場合の処理も注意が必要です。
- 購入時にすでに「消耗品費」で費用処理していた場合
→ 廃棄時点での追加処理は不要(既に費用計上済) - 購入時に「貯蔵品」などで資産処理していた場合
→ 廃棄時には「雑損失」や「消耗品費」への振替処理が必要となる場合あり
いずれにしても、廃棄処分した旨を明確に記録し、会計帳簿や在庫表に反映させることが重要です。
帳簿と実在庫のズレへの対処法
実務では「帳簿上は10本あるはずなのに、現物は8本しかない」といった在庫ズレが起こることもあります。
原因としては以下が考えられます:
- 無断で使用された
- 廃棄したが記録していない
- 他部署へ持ち出された
- 棚卸が未実施 or 誤差があった
このような場合は、棚卸しの際に差異を確認し、必要に応じて以下のような対応を行います:
- 【少なかった場合】→「雑損失」「消耗品費」などで帳簿調整
- 【多かった場合】→「雑収入」などで過去の処理見直しや調整仕訳
定期的な棚卸しと、在庫表との照合がズレ防止の鍵です。
まとめ|トナーの勘定科目は「使い方」と「社内ルール」で決まる
トナーの勘定科目には「これが正解」という唯一のルールはありません。
消耗品費・事務用品費・貯蔵品・保守費用など、用途や購入形態によって変わるため、実際の業務では迷いが生じやすい項目です。
明確な答えがないからこそ、事例を知っておくことが大切
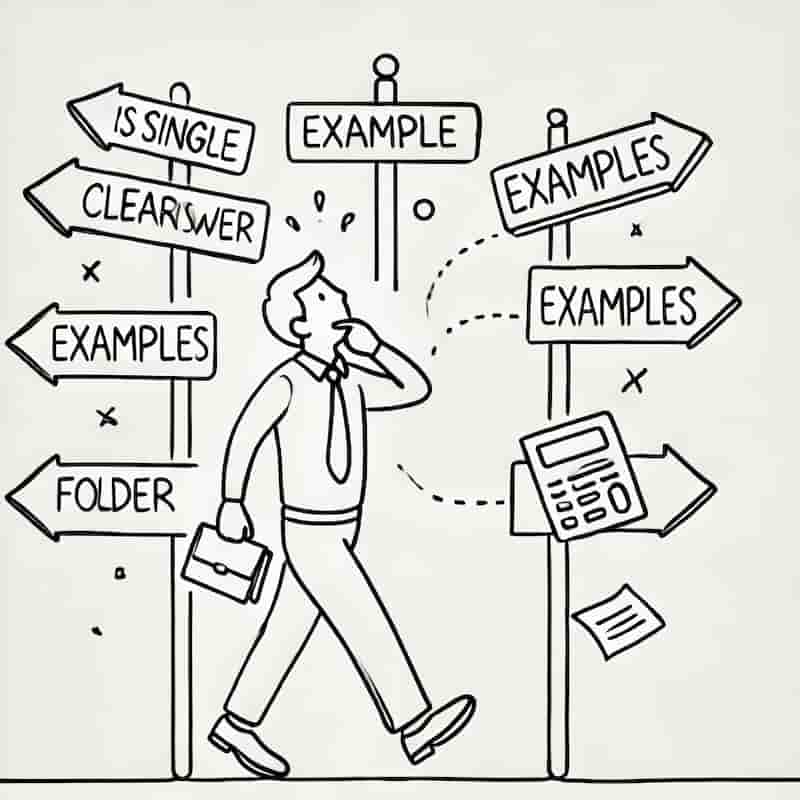
勘定科目の選択は、「自社の処理方針」や「過去の実例」によって判断するのが最も現実的です。
実際に多くの企業では、
- 少量購入は「消耗品費」
- 大量保管は「貯蔵品」
- 契約込みの費用は「保守費用」や「リース料」
といった具合に、業務内容や契約状況に応じて柔軟に処理されています。
よくある事例を知っておくことで、「これでいいのかな?」という不安を減らし、経理処理や監査時の混乱も防ぐことができます。
社内マニュアル化や共有リストの整備をおすすめ
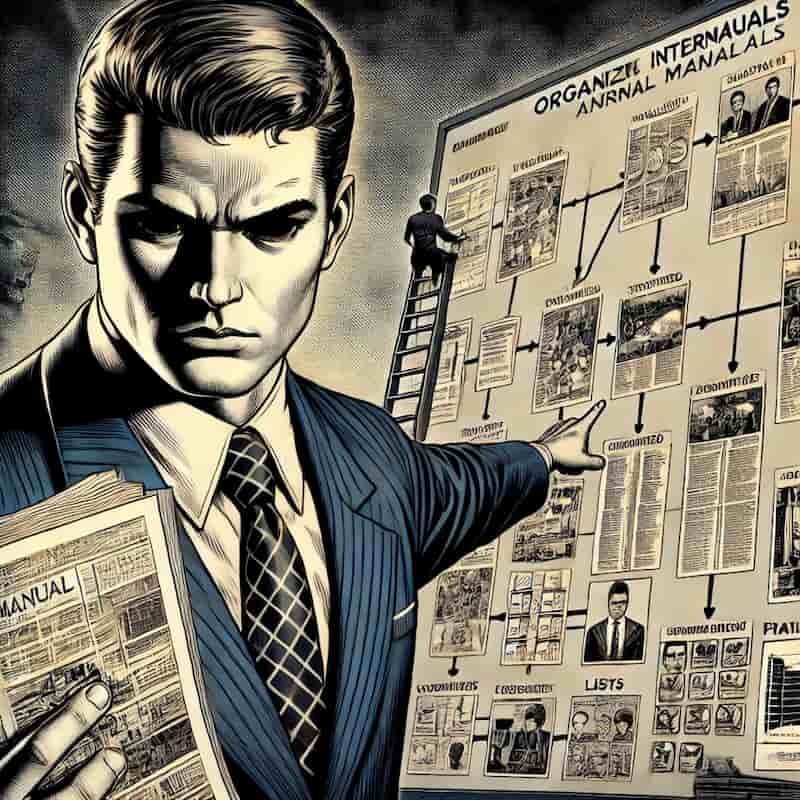
経費処理や在庫管理を複数の担当者が行う場合、処理基準や勘定科目の使い分けを明文化しておくことがとても重要です。
具体的には:
- よく使うトナー型番と、それに対応する勘定科目一覧
- 少額・在庫・リースなど、ケース別の仕訳ルール
- 経費精算システムでの入力例と注意点の共有
こうした情報を社内マニュアル化またはGoogleスプレッドシート等で共有しておくことで、
担当者が変わってもスムーズに処理できる体制が整います。
トナーは「地味だけどミスしやすい」項目だからこそ、処理の標準化とルールの明確化が、業務の安定と効率化につながります。
今回の記事が、日々の経理実務や備品管理の参考になれば幸いです。
不要になったトナーの整理・処分も、当店にお任せください。

「勘定科目の処理はできたけど、使わないトナーが残っている…」「型番しかわからないけど売れるのかな?」
そんなお悩みもご安心ください。メーカー純正・未使用トナーであれば、無料査定フォームから簡単にご相談いただけます。
仕訳処理だけでなく、在庫管理やスペース確保の面でも、トナーの買取活用は業務効率化につながります。
経理・総務担当者の皆さまにおすすめ!あわせて読みたい関連記事
トナーの仕訳処理や勘定科目だけでなく、在庫管理・コスト削減・複合機の運用・非純正トナーのリスクなど、日々の備品管理に役立つ情報をまとめました。
日常業務の効率化やムダの削減にお役立てください。
✅ トナー管理に悩んだらまずはコレ
👉 トナーの在庫・型番・誤発注を防ぐ方法|総務・庶務担当向けガイド
✅ オフィス全体のコスト削減を見直したい方に
👉 オフィス備品のコストを減らすには?すぐできる見直しポイントまとめ
✅ 複合機の入れ替え・導入を検討中の方に
👉 複合機導入ガイド2025年版|選び方・注意点・失敗しないポイント
✅ 非純正トナーの取り扱いで迷ったら
👉 互換トナー・リサイクルトナーの違いと注意点を徹底解説